 小宮友根『実践の中のジェンダー』合評会
小宮友根『実践の中のジェンダー』合評会
エスノメソドロジー |
ルーマン |
研究会 |
馬場靖雄論文書庫 |
そのほか |
 小宮友根『実践の中のジェンダー』合評会
小宮友根『実践の中のジェンダー』合評会ここには、2013年03月20日に上智大学にて開催した社会学研究互助会第五回研究会「小宮友根『実践の中のジェンダー』合評会」における配布資料などを掲載しています。
| このコーナーの収録物 | 池田 弘乃さん (配布資料) | |
| 毛利 康俊さん (配布資料) (討議) | ←このページ | |
| 全体討議摘要 |
※本書の紹介ページ![]() があります。あわせてご覧下さい。
があります。あわせてご覧下さい。
法理論の内部で、ルーマン理論に肯定的にせよ否定的にせよ言及される場合に、ルーマン理論によって法が ― とくにおのれの社会の法現実が ― どのように記述されるのかが明示されていたか?
これがあってはじめて、ルーマン理論によって、今まで見えにくかった重要な事実を視野に入れることができるようになったとか、逆に、重要な事実が隠蔽されるとか言えるはず
現実には、それほど明示されてきたとは思えない。だとすれば、肯定的言及も否定的言及も無意味では?
しかし、ルーマン自身にも責任。
ルーマンには『法の社会学的観察』という、ちっとも観察をしていない本がある。
そこで、小宮本のサブタイトル:法システムの社会学的記述 !!
ちゃんと、法の風景が描き込まれている
両者(個々の行為と集合的な秩序:毛利)を(あらかじめ因果関係で結ぶような)モデルのもとで観察する前に、ある行為がどのような構造(限定された行為可能性)のもとで理解可能になっており、かつある行為によってどのような構造が理解可能になっているかという、作動のうえに表示された構造との構成関係を記述してゆく。
(第2章78)
法的推論は常識的知識を不可欠の要素としつつ、その使用に独特の文脈を与えてもいる。法的な文脈と、その文脈における常識的知識の使用の関係は、互いが互いを理解可能に死合う関係、ちょうど2章で述べた構造と作動の相互構成関係なのである。したがってこのように、常識的知識を用いた多様な実践の一部分に、独特の境界をもった法的推論という実践が位置づいている様子は、ルーマンがいう意味で『全体社会のサブシステムとして法システムが作動している』と呼ぶのがふさわしいものなのではないか。
(第4章187)
常識的知識を用いて規則と事実を繋ぐ実践の中で、何を自明な知識とみなし、どこに疑いの視線を向けるのかという、個々の文脈に応じた複雑な事情のもとで、争いは生じているのである。(第4章188)
理由を与え求める言語ゲーム スコアキーピング
ある人がなにかを主張する = コミットメント
その主張に続けて、一定範囲のことを相手の人が主張することを許容する
その主張に続けて、一定範囲のことは主張できなくなる(矛盾)
概念の特定
どういうときにその概念が使用でき、
その概念を使用した主張からどのような主張が可能か
知覚の段階で既に概念化されている
概念のシステムは歴史的に変わる
法的思考をめぐる議論状況のなかに置いてみると・・・
構 ↓大前提の正当化・・構文論的関係 法概念を媒介にする演繹 文 ↓小前提の正当化・・意味論的関係 事実認識の問題 論 ↓判決
理論と実務を架橋する法科大学院教育なるもの、ここに注目せずしてどうする?
あれこれの「意味」が入れ子状になりながら四方八方に伝播してゆく

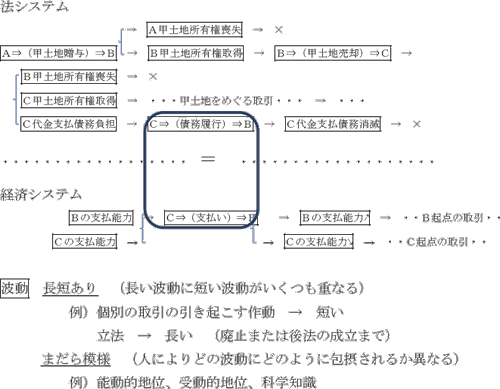
社会のなかでは多様な情報が流れ、あちこちで交錯している。情報の交錯の場に立ち会うのは人間である。それぞれに人間は自発性をもちかつ相互に別個の視座を有するので、情報交錯の場では、多様な「として」が成立しうる。この複雑な事態を分析するためにルーマンが投入するのが、一次の観察/二次の観察という区別である。一次の観察とは、ある人がある出来事を「~として観察=経験」することである。二次の観察とは、ある人がある出来事を「~として経験=観察」していることを別の人が観察することである(23)。社会の別々のところで生じた出来事が、複数の視線の交わる処で受け止められ、一つの出来事に結実すること、そしてこの出来事の結果がさまざまなコミュニケーションの現場に波及していくこと、これがコミュニケーションの過程である。一つの視点からは特定の出来事が、厳然たるリアリティとして経験されている(一次の観察)。だがもう一つの視点からは、その出来事は別様に経験されている(これも一次の観察)。ある視線が、別の視線はこれらの出来事を別様に経験しているということに気づくとき、この視線は二次の観察の次元に移行する。たとえば次のように。
Aが、Bからの契約の「申込」と見た出来事があった(Aの一次の観察)。しかし、それはBから見れば「申込の誘因」に過ぎなかった(Bの一次の観察)。AとBは、当の事実についての互い見方が食い違っていることに気づく(ABともに相手について二次の観察をしている)。結局、話合いや訴訟によって当の出来事は「申込」であったことになり、契約成立を前提にして(A、Bその他の法システムへの参加者にとっての一次の観察=法システムそのものにとっての一次の観察。この段階で初めて法システムの「作動」があったことになる)、ABその他関係者の法的コミュニケーションが続く。
してみると、前節二の法のオートポイエシスの記述は、「法システムにとっての一次の観察」=「法システムの作動」の次元だけに焦点をあてた一面的なものである。法のオートポイエシスの進行の途中には、二次の観察(潜在的ないし顕在的な法的論争)の遊動期間が挟まっており、「二次の観察の決着」=「法システムにとっての一次の観察の成立」=「法システムの作動」のたびごとに法的事実が確定し、次のコミュニケーションに接続していく。
(拙稿2013)
観察はそれ自体特定のシステムの作動であるが、自他のシステムの作動の結果に言及してゆく限りで、観察である。

特に(2)が決定的。二次の観察の対立にどう決着がつくかはゼマンティクが相当に規制しているので、これを欠くと(1)もできない。
諸システムの重合 お互いに見合って見合ってになるはずなので、どのようにして重合が起こりえているのかわからない
「私たちは会話の中でさまざまなことをおこなうが、同時に会話そのものをおこなってもいる。・・・(中略)・・・むしろ会話の中で何がおこなわれているのかを記述しようと思うならば、同時に進行している会話そのものの秩序を無視するわけにはいかないはずだ・・・
(第3章122、ジェグロフの考え方のまとめ、著者もコミットしていると思われる、強調著者)
どの社会システムに対してもななめの関係に立つ「会話そのもの」が、それ自体の秩序化装置をもっていることによって、会話そのものが進行することが可能になり、その会話の中で諸システムが重合している。
全体として、常識の方がえらい、すごいという趣旨か?
ここまで見てきたいくつかの秩序は、それぞれの相を異にする秩序である。と同時に、それらはすべて社会秩序すなわち〈意味〉によって成立している秩序である。だからそれらは、同一の時空間および物理的な身体動作のうちに、矛盾無く同時に成立することができ、なおかつそれぞれ〈意味〉的に閉じた境界を持っている。
(第2章92-93)
ルーマン『社会システム理論』第9章 実在的矛盾
これを指摘した方が、実践の現場での多様な<意味>のぶつかり合いにに気づき、どの<意味>を現実化するかの決定が重要であることに注意をうながせるのではないか。