 酒井泰斗「ルーマン解読1:小松丈晃さんと『リスクの社会学』を読む」
酒井泰斗「ルーマン解読1:小松丈晃さんと『リスクの社会学』を読む」
エスノメソドロジー |
ルーマン |
研究会 |
馬場靖雄論文書庫 |
そのほか |
作成:20150421 更新:20170524
 酒井泰斗「ルーマン解読1:小松丈晃さんと『リスクの社会学』を読む」
酒井泰斗「ルーマン解読1:小松丈晃さんと『リスクの社会学』を読む」
この頁には、2015年4月から6月にかけて朝日カルチャーセンター新宿にて開催した「ルーマン解読1」講義における質疑応答などの一部を収録しています。
小松丈晃さんによる著作紹介、講義当日の応答の再録と講義後にいただいた質問に対する回答が含まれており、署名のない項目はすべて酒井によるものです。
概要 |
第一回講義と質疑応答(2015.04.20) |
第二回講義と質疑応答(2015.05.18) |
第三回講義と質疑応答(2015.06.29、小松担当) |
これまでのルーマン像は、次々に出版される特定の時期の著作群の内容に大きく左右され・変転してきました。しかし『社会の理論』と『社会構造とゼマンティク』という二つの著作シリーズが刊行されてみると、これら膨大な著作群の多くが、30年をかけて追求された一つのプロジェクトのパーツであったことが分かってきました。(そして現在では、このプロジェクト、2シリーズのほとんどに翻訳でもアクセスできるようになっています。)
こうした事情を踏まえ、この講座では、これまでも比較的よく読まれてきたルーマンの幾つかの小品を、上記研究プロジェクトに関連付けて──また「アメリカの行動諸科学を摂取しつつ・大陸の社会理論の伝統に対峙する」というルーマンの二面性に留意しつつ──改めて読みなおします。
※ニクラス・ルーマン (著), 小松 丈晃 (翻訳) 『リスクの社会学』(新泉社)をお持ちの方はご持参ください。(テキスト持参は必須ではありません)

(期待していたことと違う、望ましくない結果の可能性としての)リスクという観点から観察されているという事実から、逆に浮かび上がってくる全体社会の「ノーマルな成り行き」とは、一言でいえば、「決定への依存性」です。もう少し詳しく言えば、「未来は、現在下されつつある決定に、あるいは、それがすでに下された決定であるならば、もはや修正できない決定に依存しているという現実」(12)です。こんにち、ある損害を引き起こす可能性のある事象が「リスキー」なものとして語られるとき、人々はその背後に(自分自身をも含めて)誰か(あるいは何らかの組織)の決定を(たとえば「人災」として)読み取ろうとします(帰属)――たとえ、実際には誰かや何かの決定に完全に帰属できない事案であっても――。そうした帰属のやり方を観察しよう(観察の観察)というのがルーマンのスタンスになります。
リスクをこのように「決定依存性」という近代社会の(あらためて指摘するまでもないほど)ごく基本的な構造的特徴と結びつけ、あらゆる決定に内在する一般的な現象として捉えたことにより、リスクは、科学技術やエコロジー問題や健康問題などに限定されなくなります。ルーマンの場合、リスクというテーマは「近代社会の理論」の一部で、「近代社会の理論」の概念装置をとおして特徴づけられるべきものです。けれどもそのような理論は、彼によるとまだ存在していません(22)。それゆえに原子力発電所のような高度な科学技術は、リスクを社会学的に考察する上では、たいへん重要だが数あるリスク現象の一つとして取り扱われることになります(「特殊事例」としての「ハイテクノロジー」(本書第5章))。このように近代社会の理論の一部としてリスクのテーマをとらえるという視点からすると、なによりも「機能分化」という全体社会の構造を問題にしなくてはなりません。たとえば、機能分化した全体社会のサブシステム(各機能システム)も、それぞれ固有の(真か偽か、法か不法か、与党か野党かといった)「二元的コード化」を通して、機能システムに固有のリスクを著しく生み出している、とルーマンは見ています(第4章)。各機能システムは、あらゆる出来事・事象に(あまりなじみのない出来事にも)この二元的コードを適用することを強いられ、しかも、コードのいずれの値(「真」なのか「偽」なのか)になるのかは、倫理や道徳などが決定するわけではなく、その決定の自由は各機能システムにゆだねられています。そのため、「事後的に振り返ってみると、つねに他方の値も考慮されえたかもしれない」(102)というリスクがそこに内包されているからです。また、第8章(政治)、第9章(経済)、第11章(科学)では、政治、経済、科学それぞれにとっての固有のリスクについて論じられます。
さらに、他者に不利益をもたらさずに自己の利益を追求できる事例などは――かつての、〔1〕の引用文に記されているような「茸狩をする人々」、「冒険に身を投じる集団」であればありえたかもしれないけれども――いまやまったく存在しない、とされます。むしろ、リスキーな決定には「社会的なコスト」が伴われるのであり(これを第4章では「時間拘束」として議論されている)、そうした決定によって、「自分で下すわけでも制御できるわけでもない決定によって危険にさらされている」(130)と見なす被影響者が生み出されます。すなわちリスキーな決定により、「決定者」と「被影響者」の間の溝という近代社会の「根本問題」が生み出されるわけです(決定者/被影響者を、ルーマンは第6章で「決定の形式」とも呼んでいます)。「決定」に伴うリスクという観点からすると、全体社会は、このような決定者と被影響者の間の乖離として把握されます。
この両者の溝は、かつては「信頼」によってある程度は架橋されていました。けれどもルーマンによれば、今日的なリスク現象に関しては、信頼にこうした役割を期待するのは困難です。また、確かに「コミュニケーション」への期待感は依然として(現在でも)根強いけれども、彼の見るところでは、より多く両者がコミュニケーションをすることで問題が解決に向かうという考え方は支持できません。同様に、「参加」や「より多くの情報を」という処方箋も困難を抱えます。このように、一見するとルーマンの議論運びは「八方ふさがり」な状態を指摘しているだけのようにも思えますが、最終章において(あるいは本書の後に刊行された別の論文でも)「了解(Verstandigung)」とか「リスク・ダイアローグ」という言い方で、決定者と被影響者の間でのコミュニケーションの形式の可能性を示唆はしています。ただしこの論点に関するルーマンの記述は本書においてはごく薄いものにとどまっているので、すでに多様なかたちで実践されている「リスク論議」の諸形態の意味と問題点を経験的に観察しその可能性を探るといった関心からすると物足りないものが残るでしょう。
すでに示唆されているとおり、リスク現象に関する「厳密に社会学的なアプローチ」とは、コミュニケーションの意味のみに焦点を合わせるものです。たとえばリスクを、何らかの科学技術や物質などに付随する負の属性としてとらえるやり方では、社会学的な観察の可能性は限定されたものにとどまり、またなによりも、「何をリスクと見なすのか」というリスクの選択が、集団や文化や個人ごとに多様だ、と主張してきたはずの社会学自体が、「近代の生み出した科学技術こそリスキーだ」というかたちですでに「何がリスクか」の選択を遂行してみせてしまうのは、こうした主張と相容れません(21)。
ルーマンは、「リスク」をコミュニケーションと関連づけて把握するために、リスク概念そのものの刷新も企て、上記のとおり「決定」を軸として議論を展開します。すなわち彼によると、リスクとは、将来の損害可能性に関して、起こりうる損害が自己(個人や社会システム)の決定の帰結と見なされ、当該決定に帰属される場合をいい、他方、起こりうる損害が、自己以外の外部からもたらされるものだと見なされ、外部の誰か・何かに帰責される場合、その将来的損害可能性は「危険(Gefahr)」とされます。ここでいわれている「決定」とは、意識過程のことではなく、「諸選択肢の中からの選択の帰属のコミュニケーション」を意味します(当人が「決定を下した」と意識せずともコミュニケーションの中でそう見なされることはよくあるし、何もしないでいることも一つの「決定」となります)。
本書はいまから20年以上前に刊行されたもので、リスクと危険の区別などはすでに社会学の中ではなじみのものになった感がありますし(というよりも、この区別だけが個別に取り出されて受容され、それゆえの誤解も見受けられるのは残念ですが)、じじつU.ベックも90年代になると、この区別をみずからの著作の中でもしばしば使用するようになります。ただ、本書が刊行された当時の脈絡に沿っていえば、上記の通り、厳密に社会学的なリスク研究の端緒を開いた研究として評価できるでしょう。当時、「リスク」といえば基本的には保険数理や疫学などでの定量的な論じ方が主流であった中で、M.ダグラスらの業績(1982)やU.ベックの『危険社会』(1986)、P.スロヴィックによる心理学的アプローチなど、人文社会科学系の領域からの貢献が芽生えつつありました。ただこうした領域においても、たとえば専門家/素人という枠組の中での両者の心理的な解釈の相違を問題にしたり、個々人や各集団のおかれた多様な文化ごとのリスクの構成のされ方に言及したり、あるいは何らかの巨大装置や物質等に付随する負の「属性」としてリスクを語る、といった取り上げ方が注目されていましたが、そのような流れの中で、本書ならびにその前後に公刊された論文において、ルーマンが、セカンド・オーダーの観察の位置からコミュニケーションや決定とリスクを関連づけ、帰責のプロセスや齟齬などをも問いうる道筋を作り出した点は、評価されてよいでしょう。
また、これとも関連しますが、主としてテクノロジーやエコロジーの問題と(のみ)直結させて語られてきたリスク現象を、機能分化という近代社会の構造に深く埋め込まれたものとして捉え返し、より一般的な広がりをもって観察できるようにした点も、本書の意義の一つといえます。もっともこれは、ルーマン自身がそれまで、システム理論の観点から「社会の理論(Gesellschaftstheorie)」の構築に取り組んできていたがゆえに可能であったわけですが、近代社会のサブシステム(機能システム)や各組織が、それぞれ固有の論理にしたがってリスクをいかに構成し処理しているのか、またそのことが各(機能)システム自体にどういった過剰負担を招き、あるいは他のシステムや環境(人間や生態系)にいかなる新たな問題を作り出すのか、等といった論点を、各機能システムの作動の仕方に沿って明らかにしたり、またこの点で、経験的研究に接続していく可能性も生み出されました。本書の評価は、このほかにも様々な観点から可能でしょうけれども、さしあたりは以上の二つのみ指摘しておきたいと思います。(小松丈晃)
|
|
第1章8段落に、「全体社会が全体社会を反省する」とありますが、これはどういうことでしょうか。
※参照箇所:
[0-8] [害の存在が科学的に確認されている時ですら、リスクを巡る争いは生じる。] まさにそれゆえに、この問題は社会学的に興味深いのである。というのは、ここから読み取れるのは、ということだからである。… 正常性という形式[つまり〈正常/逸脱〉や〈正常/異常〉といった区別]の分析が問題なのだという出発点を受け入れるのであれば(…)、何がそこで起こっているのかに関するより正確な究明のみが[社会学にとっての]課題となる。(訳 14頁)
- 全体社会が、その時点で人を説得させる力をもつ災いのゼマンティクを用いて、全体社会の正常性を反省しているということ、
- またいかにして反省しているのか
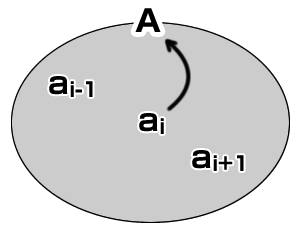 STEP 1.
STEP 1. [0-7] リスクに満ちた行動が、カタストロフィをもたらしうると想定される場合にはつねに、計算の拒絶でもってこれに反作用される。カタストロフィの閾をどこに設定するかは、ほとんど、これを議論する人の好みにゆだねられる。いずれにせよ、この論点が合意に至ることはありえない。にもかかわらず、犠牲者さえ見つけ出せればそのかぎりで、コミュニケーションは道徳化されうる。これにより、こうしたリスクに敵対的な人々は「将来世代」という定型句を口にするようになる。…カタストロフィが生じないように努力すべきだという倫理は一般化され、すべての人に対して強制され道徳的に要求されうるものとなる。また人は自分自身のことだけを考えているのではなく、他者のことをこそ、さらにはまだ生まれていない者のことをこそ考えるものだという形で道徳が強化される。…(訳 13頁)
- p.15 に出てくる「システム準拠」とは何ですか。
- 「全体社会という システム準拠 から出発する のであれば」ということは、そこから出発しないことはできるし、出発しないことも出発するのも等価だということですか。
- でも実際には、ルーマンは、全体社会というシステム準拠から出発すべきだと思っている、と考えてよいですか。
ルーマンの主張に関わりなく一般論として、「Aから出発するのであればBだ」と述べるときには、「Aから出発しないこともできる」ことは前提となっているでしょう。それはしかし「Aから出発すること と A以外から出発することは等価だ」ということは含意しないでしょう。ですから、二番目の質問に対する答えは──ルーマンの主張に関わりなく──「否」です。そう応えた上で、1番目と3番目の質問について考えてみますと。
※参照箇所:
[0-10] こうした[リスク現象の]分析では、決定と技術の概念が(…)重要な役割を果たす。それだけにいっそう、これらが決して心理的な事態や物質的な(機械のような)事態を意味しているのではない点を前もって示しておく必要がある。全体社会の分析は、コミュニケーションのみを対象としている。… もちろん、だからといって、全体社会システムの環境の中には、観察者が意識とか機械として指し示せる現実など存在していないのではないか、などと疑っているわけではない。しかし、全体社会という システム準拠 から出発する のであれば、これらの意識や機械は 全体社会システム の環境としてのみ考察対象となる。(p. 15)
・・・というほどのことを言っていることになります。
- 「決定」とか「技術」とか聞くと、読者はまず、「(決定する人の)意識」や「(技術を現実化する)機械」のことを思い浮かべるかもしれないが、
- それらは、本書が照準している〈コミュニケーション(=システム)/コミュニケーションではないもの(=環境)〉という区別でいうと、後者に属する。
- そうしたものについては、本書では、「それに関わるコミュニケーションにおいてどう扱われているのか4」という観点から検討する。
ルーマンは、全体社会というシステム準拠から出発すべきだと思っているかどうかという点について言えば、「このやり方で検討できることがある・このやり方でなければ検討できないことがある」と考えているからそうしているわけでありましょう(実際──常識的に考えて──その通りではあろうと私も思います)。
〈内容的次元|社会的次元|時間的次元〉の区別の具体的なイメージが浮かびません。リスクに関して、具体的な例を教えて下さい。
国家理性、構造的ドリフト、リスク合理性、ラディカル構成主義、普遍と個別の結合、リダンダンシー、悪魔、ロマン主義 などについて説明してください。
上記のうち、講義で扱う序文と第一章に登場する二つについて述べます。
本を読むときには、〈知らないと分からないこと/知らなくても分かること〉を適切に区別しなければなりません。〈知らないと分からないこと〉は調べればよいだけですが、〈知らなくても分かること〉は 調べても分からない のです。もしかすると質問者さんは、「国家理性という言葉を知らないためにこの箇所が読めない」と思っているかもしれませんが──以下その前提で回答を記しますが──、そうではないかもしれません。
[1-2-4] と [1-2-5] の二つの段落は、次のようなペアになっています。「国家理性」は、このうちの「どのような問題ではないのか」のリストの中に、その一つとして登場するものです(という前提のうえで、事典を引いてみてください)。
- [1-2-4] 以上の手短な示唆からまず次のような第一印象がもたらされる。すなわち、複雑な問題が背景にあって、それは確かに〔リスクという〕概念の発見によって関心が持たれるようになったものだが しかし この概念によっては十分に指し示されない、という印象である。
- 重要なのは、確かな予測に基づいたたんなるコスト計算ではない。〔以下、これがどのような問題でないかの一覧。略。〕
- [1-2-5] リスクという言葉の歴史からだけでは、これについての確かな回答は得られない。〔とはいえ〕その歴史から、若干の手がかりは与えられている。
- とりわけ、合理性要求が、時間とますます厄介な関係に入り込んでいるという点は手がかりになる。合理性要求と時間の双方は連動しあって、次のことを指し示している。
- すなわち、未来を十分に知りえないにもかかわらず、しかも、自身の決定によって作り出される未来を決して知らないにもかかわらず 時間を拘束している決定こそが重要だ、ということをである。
※登場箇所
技術的な装置と関連したリスクが判明すると、ますます、このリスクの制御のために雇用された人間を選んで信用することになる。もしくは その他の種類の冗長性 をあてにすることになる。(p.47)
「ルーマンによるパーソンズの書き換え」について、ルーマンは2つのことを調停しようとしていた(ができなかった)と述べていましたが、その「2つ」とはなんですか。
ルーマンはいろんな分野について本を書いていますが、そもそもどういう関心で・何がしたくて こうした仕事をしたのでしょうか。例えば「組織」について、たとえば「法」についてなど、その分野分野で問題を探してはそれについて考えているのか、それとも何か基本的な関心があって それに関わる問題を論じているのか。
|
|
|
「危険との対照においてリスクを捉えるというルーマンのリスク規定には、社会的な偶発性に目を向けさせるという狙いがある」という話がありました。では、「誰のせいなのか」〔社会次元〕ということを度外視し(あるいはその点には意見の齟齬がないので)、もっぱら「何のせいなのか」「どうすればよかったのか」という点を問うことにした場合、これはリスクの問題ではなくなるのでしょうか。
「誰が決定したか」に齟齬はないが、「どんな決定だったのか」については齟齬がある場合、これは「社会的次元」と呼んでいいのでしょうか。
「〈リスク/安全〉から〈リスク/危険〉に切り替えるメリットは、帰属概念を使えることだ」という話がありました。ということは、「〈リスク/安全〉だと帰属概念は使えない」ということでしょうか。
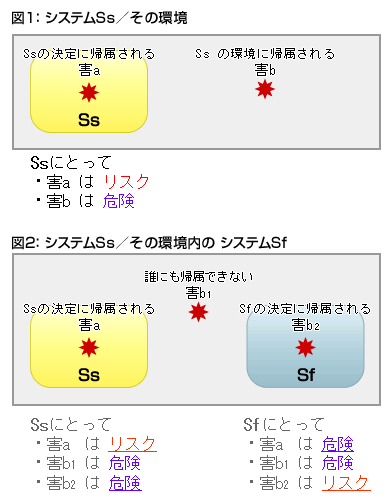
「ルーマンは、〈(ある人にとっての)危険〉という語を、〈その人には帰属できない原因によって生じた害〉に関わるものとして使おう、と提案している」という話がありました。その場合、害の原因は、と理解してよいでしょうか。
- [1] その人以外の誰かに帰属できるものもあれば
- [2] 誰にも帰属できないものもある
- 社会心理学における帰属研究の紹介がありましたが、ルーマンはこれをリスクという主題だけに使っているのでしょうか。それとも他の主題についても使っているのでしょうか。
- 帰属研究をもう少し詳しく知りたいときに読むとよい本を紹介してください。
…行為者と観察者の間の一般的な帰属の差異が、親密な関係においても、それどころか親密な関係においてこそ、確立されうる。行為者はより強く状況に指向し、観察者はより強く人格のメルクマールへと帰属させている。…そのようにして、自動車の運転手は、自らが最善の能力とともに状況の方へと向いていると信じている。同乗者は、彼を観察し、その運転の仕方の特異さを人格のメルクマールへと帰属させる。そして、… 同乗者は自身ならどう運転し、あるいはどう運転してもらいたいのかについてコメントを加え、伝えることを求められていると感じている。それに対して運転手は、彼の行動の根拠をそのつどもっぱら自らの背後にもっており、それどころか、その根拠をその状況の文脈において体験しており、同乗者との個人的な関係の水準でその根拠を大幅に変更することは決してないのである。そのようにして、結婚は天国で結ばれ、自動車の中では解消されている。なぜなら、コミュニケーションによる処理から大幅に遠ざかるような 帰属コンフリクト Attributionskonflikte が生じているからである。これを見れば、〈危険/リスク〉という区別が、「帰属のコンフリクト」という上位論題の 一つの下位論題として登場してくることが確認できるでしょう。
(『社会システム理論』1984=1993 359頁)。
「〈リスク/危険〉区別は ルーマンの議論の中では比較的広範囲に影響を与えたものだが、誤解もかなり多い」というお話がありました。なぜそうした誤解が生じるのでしょうか。
危険とリスクの区別だけでもって、すべてのケースを分類できるのでしょうか。危険なのかリスクなのか曖昧な場合・どちらともつかない場合もあるのではないですか。こういう区別をする意義はどこにあるのでしょうか。
これはとても重要な疑問です。
どういう意味で重要なのかというと、これが、まさに前項(Q2b05)に記した 〈危険/リスク〉区別をそれ単独で扱ってしまった ために生じる疑問の典型例である、という意味においてです。そして驚くべきことに この誤解は、社会学その他の専門家が書いた学術的な論考などにおいすら、ほんとうに よく見受けられるのです。
この講義は、こうした疑問に応えるために おこなったところもあるのですが、しかし実際には講義においてそれほど時間をかけて説明することが出来なかったポイントでもありますので、あらためて もう少し丁寧に敷衍してみましょう。
まず、もういちど三つの図式の関係について簡単に振り返っておきましょう:
この講義には「社会システム」の話が出てきませんが、なぜでしょうか。不要だということでしょうか。
|
|
|
『リスクの社会学』に先行する研究として、の紹介がありました。ベックの『危険社会』とルーマンの議論の関係、違いを教えてください。
- Ulrich Beck, Risikogesellschaft, 1986.〔=東・伊藤訳『危険社会』法政大学出版局, 1998年〕
- Mary Douglas & A. Wildavsky, Risk and Culture, 1982
ベックが、近代を二つに分けて、リスクが問題になるのは第二の近代においてだと述べるのに対し、ルーマンはこのような区別を認めません。近代に関するベックとルーマンのこうした考え方の違いと、リスクに対する両者の見方の違いには関係があるのでしょうか。
| 序文 | |
| 第1章 | リスクの概念 |
| 第2章 | リスクとしての未来 |
| 第3章 | 時間拘束──内容的観点と社会的観点 |
| 第4章 | 観察のリスクと機能システムのコード化 |
| 第5章 | ハイテクノロジーという特殊事例 |
| 第6章 | 決定者と被影響者 |
| 第7章 | 抗議運動 |
| 第8章 | 政治への要求 |
| 第9章 | 経済システムにおけるリスク |
| 第10章 | 組織におけるリスク行動 |
| 第11章 | そして科学は? |
| 第12章 | セカンドオーダーの観察 |
いまお話に出た〈規範|希少性|リスク〉については、前回までの講義では、機能分析のパーツ──時間拘束に対する三つの解決類型──として説明がありました。
そのことと、さきほど話にでた近代社会の歴史的変化の記述とは、どのような関係にあると理解したらよいのでしょうか。
| 序文 | |
| 第1章 | リスクの概念 |
| 第2章 | リスクとしての未来 |
| 第3章 | 時間拘束──内容的観点と社会的観点 |
| 第4章 | 観察のリスクと機能システムのコード化 |
| 第5章 | ハイテクノロジーという特殊事例 |
| 第6章 | 決定者と被影響者 |
| 第7章 | 抗議運動 |
| 第8章 | 政治への要求 |
| 第9章 | 経済システムにおけるリスク |
| 第10章 | 組織におけるリスク行動 |
| 第11章 | そして科学は? |
| 第12章 | セカンドオーダーの観察 |