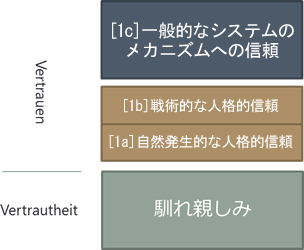講義概要
1968年に刊行された著作『信頼』は、特に日本では著名な倫理学者によって邦訳されたこともあずかって、ルーマンの著作の中では比較的広く読者を得たものです。しかし、なぜこの時期にこのような形で信頼を取り上げなければならなかったのか、そしてまた ルーマン理論のなかで信頼という論題がどのような位置にあるのかは、それほど判明ではありません。
後期の著作群『社会の理論』の方から振り返ってみると、これが、ルーマン流の近代化論の内実を与える社会学的時間論を構築するための一論題として扱われていることが見えてきます。そこで本講義では、
- 第1講義[小宮担当]において、ルーマンがジンメルとゴフマンに依拠しながら、エリアスを意識しつつ描いている
- (1)「それほど親しくない人への・その人の自己表現にもとづく信頼」が必要とされ・また可能になる(したがって、また「必要となる」ことが可能になる)論理的な条件としての機能分化した社会への転換と、
- (2) それにともなう行為の帰属先としての「個人の人格」の前景化、そして、
- (3) それによるダブル・コンティンジェンシーという形での複雑性の増大、という
文明化の過程のストーリーを、
- 第2・3講義[酒井担当]において、
- (1) こうした議論を展開する際にルーマンが学び・議論の基礎として用いた行動科学的信頼論(モートン・ドイチェによる社会心理学的実験研究)と、
- (2) 信頼と並んでルーマンがおこなっている 規範、契約、所有、リスク、危険といった論題との時間的観点からの比較を
紹介することで、この著作に新たな光を当ててみたいと思います。
ゲスト講師紹介 
- 小宮友根(東北学院大学経済学部共生社会経済学科准教授)
- 東京都立大学大学院社会科学研究科社会学専攻博士課程修了。専門はエスノメソドロジー/会話分析、ジェンダー論、理論社会学。司法におけるジェンダー問題に関心をもち、現在は裁判員裁判の研究、とりわけ裁判員評議の会話分析研究に取り組んでいる。
著書:
(新曜社、2011)、「評議における裁判員の意見表明」(『法社会学』77号、2012)、「裁判員は何者として意見を述べるか」(『法社会学』79号、2013)、「強姦罪における『被害者資格』問題と『経験則』の再検討」(陶久利彦編『性風俗と法秩序』尚学社、2017年)など。
ページの先頭へ
(小宮友根)
『信頼』著作概要
- Q01. 本書で ニクラス・ルーマンが 取り組んだのはどのような課題ですか。
まだ本を読んでいない方を念頭に、「何について書かれた本なのか」を教えてください。
- Q02. それぞれの課題に対して、ルーマンが与えた回答はどのようなものですか。
すでに本を読んだ方にとっての再読のガイドとなることを狙って、この本のポイントがどこにあるかを教えてください。
- Q03. こうした課題に取り組むことにはどのような意義がありますか。
本書に直接記されていないことやアカデミックな文書の中にはふつう記されないが 知っておくと理解に資するような背景的な状況・文脈などを伝え、読者が、より広いコンテクストのなかで本書の評価を行えるよう手助けをしてください。
Q1. 本書で ニクラス・ルーマンが 取り組んだのはどのような課題ですか。
本書でルーマンが取り組んでいるのは、「信頼」と彼が呼ぶものを機能分析の対象とするという課題です。ここで「信頼」と呼ばれるのは、「相手が然々の仕方で行為するならば何らかの利益が生じるが、手持ちの情報だけでは相手が然々の仕方で行為すると確実には言えないところで、しかし相手が然々の仕方で行為することをあてにして自分も行為する」ということです。たとえば待ち合わせ場所に急ぐとき、あるいは「国産」と書かれた高い牛肉を買うとき、私たちは待ち合わせ相手や売り手を「信頼」しているということになります。
他方、「機能分析の対象とする」というのは、対象がどんな問題に取り組んでいるかに注目し、同様の問題に取り組んでいる他のものと比較しながらその特性をあきらかにするということです。ルーマンが本書で信頼の「働き」とみなしているのは「複雑性の縮減」です。複雑性の縮減とは、大雑把に言えば、可能性(ここでは特に他者がどう行為するかについて想定しうる可能性)が絞り込まれることです。たとえば道ですれ違う人が自分に殴りかかってくる可能性は理屈の上では常にあるわけですが、そうしたあらゆる可能性を想定して行為しなければならないとしたら私たちは社会生活を送れなくなります。逆に言えば、私たちの社会生活は、想定される可能性が絞り込まれる(複雑性が縮減される)ことで成り立っています。「信頼」には、そうした働きがあるとルーマンは言っているわけです。
信頼のこうした働きを捉えるうえで、ルーマンは社会システム論を採用することで、複数の行為が繋がってまとまりが作られている(社会システムの存続)という事態から信頼について考えます。社会システムが存続するためには複雑性が縮減されなければなりませんが、複雑性を縮減する働きをもつものは信頼以外にもあります(ルーマンや法や組織を挙げています)。では、他ならぬ信頼によって複雑性が縮減されることは何を可能にしているのかと問うわけです。
Q2. それぞれの課題に対して、ルーマンが与えた回答はどのようなものですか。
二つの側面を持つ回答を与えています。一つの側面は、信頼による複雑性の縮減は、社会が高度に複雑化すること(機能分化)を可能にしている、というもの。もう一つの側面は、機能分化が成立しているからこそ、信頼することが容易になっているというものです。
機能分化というのは、経済、政治、科学などの領域ごとにそれぞれ独立の社会システム(機能システム)が成立することです。この機能分化の成立に「信頼」がどのようにかかわっているのかを論じるためには、ルーマンは「馴れ親しみ」「人格的信頼」「システム信頼」を区別して対比しています。
「馴れ親しみ」とは簡単に言えば、「これまでやってきたとおりにやる」以外の可能性が意識されていないことですが、機能分化した社会ではある行為がどのシステムに属するかには常に複数の可能性があるので、馴れ親しみではコミュニケーションを支えられません。「人格的信頼」は相手の人格にもとづいて相手が然々の仕方で行為することをあてにすることですが、機能システムが成立するためには見知らぬ人どうしの行為も繋がることができなければなりませんので、人格的信頼も機能分化を支えるには不十分です。
それに対して「システム信頼」は、象徴的に一般化されたコミュニケーションメディア(SGCM)に対する信頼です。SGCMとは、特定の機能システムにおいてどんな行為の繋がりが可能なのかを示してくれる象徴のことです。経済システムなら「貨幣」、政治システムなら「権力」、科学システムなら「真理」がそれにあたります。そうしたメディアは、「売買」「集合的意思決定」「知識・情報の獲得・伝達」にかかわる行為どうしの繋がりを仲立ちします。SGCMに対する信頼があると、見知らぬ相手に対してであっても、そうしたメディアのもとで相手が行為することをあてにできるようになります。こうして、「システム信頼」という特殊な信頼は機能システムの成立を可能にしているというわけです。
他方、SGCMは当然のことながら機能分化とともに成立しているものです。従って、システム信頼という信頼――非人格的であるがゆえに学習が容易で、期待外れに強く、信頼しているということすら通常は意識されない強固な信頼――の様式の成立は、機能分化が準備したものでもあります。機能分化と信頼が相互に成立条件を提供しあっているこの関係への注目が、本書の醍醐味となっています。
Q3. こうした課題に取り組むことにはどのような意義がありますか。
「どんな意義があるか」よりもまず、「何に使えないか」を確認しておくことが重要かもしれません。とりわけルーマンの議論から、日常的な意味での「信頼」について何か教訓めいたものが引き出せると考えることには慎重さが必要です。ルーマンを読んでも、どんな人が信頼できるのかや、どうやって他者と信頼関係を築いたらいいのかはまったくわかりません。ルーマン自身、そうした問い(「倫理学的問い」と彼が呼ぶ問い)と自分の仕事の違いを繰り返し強調しています。実際、ルーマンが「信頼」と呼ぶものは、日常的な意味での「信頼」よりも広いもので、ほとんどすべてのコミュニケーションにかかわるもののようにも見えます。そうであるなら、本書の「信頼」という概念はある種のインフレを起こしているとも考えられるでしょう。
では、そうした議論から私たちはどんな意義を引き出せるでしょうか。ひとつの読み方は、ここには「社会秩序」についての(当時の)新しい視点があるのだと理解することだと思います。確かに私たちの社会ではたくさんの人がそれぞれ自分で選択しながら行為しているわけですから、そのたくさんの選択が噛み合って機能システムが成立しているなどというのは途方もなく複雑なことのように思えます。けれど上でも述べたように、複雑性の増大とその縮減相互に関連して生じているものです。すなわち、「社会はいまや単一の原理もとで皆が一様に行為しているまとまりではなく、各自が自分の選択で行為している人たちの集まりである」(奥行きのある分節化された人格を備えた・自由な個人からなる社会)というイメージは、それ自体機能分化した社会のもとで初めて出てくるものなのです。こうした視点は、たしかに行為の合理性や、価値規範の共有から社会秩序の成立について考える視点とは大きく異なるでしょう。
こうした読み方は、たとえばジンメルの社会分化論、ゴフマンの自己呈示論、あるいはルーマン同様「信頼」について考えることから出発したガーフィンケルのエスノメソドロジ-とルーマン理論の関係を考える上で、興味深い手掛かりを与えてくれると思います。私たちはいわば、「社会学的思考の遺産」を比較検討する視点を手にすることができるわけです。

![]() )。 小宮友根さんによる著作紹介、講義当日の応答の再録と、講義後にいただいた質問に対する回答が含まれており、署名のない項目はすべて酒井によるものです。
)。 小宮友根さんによる著作紹介、講義当日の応答の再録と、講義後にいただいた質問に対する回答が含まれており、署名のない項目はすべて酒井によるものです。